
2022年頃から大規模言語モデルを活用した生成AI(人工知能)が一般的に広く認知されるようになり、近年ではOpenAIが開発した対話型AIの「ChatGPT」をはじめとした多くの生成AIツールが世界中で活用されています。
今回は、生成AIツールの中でも多くのビジネスシーンで活用されている「ChatGPT」「Copilot」「Gemini」「Claude」それぞれの特徴や活用時の注意点について解説します。
まず、生成AIツールの仕組みや種類について解説します。
生成AIツールとは、文書・画像・コードの生成やデータ分析といった幅広いタスクを自動的に生成できる、人工知能技術を駆使したツールのことです。マニュアル作成からクリエイティブな作業まで、多くのビジネスシーンで活用されています。
生成AIには、機械学習とディープラーニング(深層学習)と呼ばれる技術が用いられており、AI自ら大量の学習データを自動的に学習したり、データから自動的に特徴を抽出し学習しています。この技術により、精度の高いデータ処理を行ったり新たな回答・コンテンツを生み出したりすることが可能になりました。

生成AIツールは、生成可能なコンテンツの種類が大きく分けて4つあり、性質がそれぞれ異なります。用途に応じて生成AIツールを選定し活用することで、より的確な回答・コンテンツを生み出すことができます。
文章を生成するAIのことです。テキスト生成は、人と会話しているかのような「対話型」、文章を要約・翻訳する「要約型」、ブログ記事・メールの文章などを生成する「記事作成型」、プログラミングコードの記述やエラーを検出する「コード生成型」があります。生成AIツールの種類によって用途ごとに特化しているツールもあれば、すべての用途に対応しているツールもあります。
テキスト生成するAIツールとして、OpenAIが開発した「ChatGPT」やGoogleが開発した「Gemini」などが挙げられます。
写真・イラスト・ロゴなど、さまざまな画像を生成するAIのことです。画像生成は、テキストの指示によって画像を生成するため、デザインのスキルが必要ありません。
画像生成するAIツールとして、Midjourneyが開発した「Midjourney(ミッドジャーニー)」やStability AIが開発した「Stable Diffusion(ステーブルディフュージョン)」などが挙げられます。
テキストの指示や画像をもとに動画を生成するAIのことです。現時点では動画生成できる動画の長さは数秒ほどのため、PR動画や教育コンテンツといった短い動画作成時に活用されています。
動画生成するAIツールとして、Runway社が開発した「Runway Gen-2」やOpenAIが開発した「Sora」などが挙げられます。
テキストの指示をもとに音声を生成するAIのことです。学習した声色を使用するため収録する必要がなく、さまざまな文章を読み上げたり音声を付加したりすることができます。
音声生成するAIツールとして、Microsoftが開発した「VALL-E」やGoogle Cloudが開発した「Text-to-Speech AI」などが挙げられます。
その他にも、音楽の生成やスケジュール調整、3Dモデリングの作成など、用途ごとに特化したさまざまな生成AIツールがあります。

上記に記載したように生成AIツールにはさまざまな種類のツールがあります。
次に、多くの企業で活用されている生成AIツールの中から「ChatGPT・Copilot・Gemini・Claude」それぞれの特徴について解説します。
ChatGPTは、OpenAIが開発した対話型の生成AIツールです。大量のテキストデータからの学習と継続的な学習を行っているため、会話の流れを理解したうえで、人と会話しているような自然で流暢なテキストを生成することが可能です。
幅広い知識に基づいた適切な回答、ブログ作成、メール作成、アイデア出し、文章の校正といった文章作成、文章の翻訳・要約など、幅広いタスクに活用できます。
特に「適切な回答、文章の生成、翻訳、アイディア出し」などが得意とされているため、創造的な分野で活用したい場合におすすめの生成AIツールです。

Copilotは、Microsoftが開発した対話型の生成AIツールです。Copilotでは、Bingの検索結果を利用して調査・情報収集しているため、常に最新の情報を提供してくれます。
Copilotには無料版や有料版など全部で3種類あり、そのうちの一つであるMicrosoft 365 Copilot(法人向けの有料版)は、Microsoft365アプリ(Word、Excel、PowerPointなど)と統合されているため、文書・画像・コンテンツ作成、コード作成、データ分析、プレゼンテーション資料の作成、スケジュール管理など、幅広いタスクに活用できます。
特に、WordやExcelといったMicrosoft製品を利用する日常業務の生産性を高めたい場合や高度なプログラミングコードを生成したい場合におすすめの生成AIツールです。

Geminiは、Googleが開発した対話型の生成AIツールです。Geminiでは、Googleの検索結果を利用して調査・情報収集を行っているため、常に最新の情報を提供してくれます。
また、マルチモーダルなモデルのため、テキストや動画・画像・音声など、さまざまな種類のデータを一度に認識し、処理することが可能です。そのため、テキストと視覚的な手がかり両方のデータを組み合わせて回答やコンテンツを生成するなど、複雑なタスクに活用することができます。
「文章作成、データ処理、コード作成、要約」など、さまざまなタスクに対応していますが、特に高度な論理的思考が必要になる戦略立案や問題解決に活用したい場合におすすめの生成AIツールです。
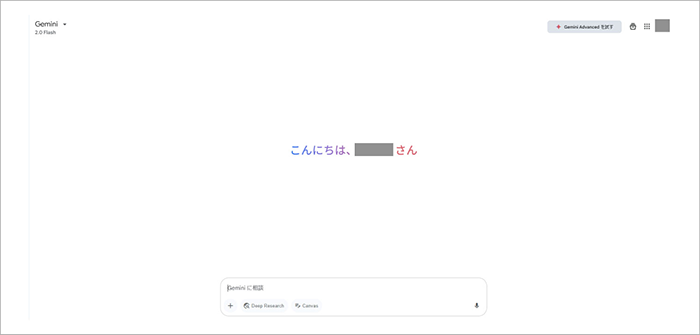
Claudeは、Anthropic(アンソロピック)が開発した対話型の生成AIツールです。Claudeは、人間が書いたような自然な表現や倫理観に配慮した文章の生成、長いテキストへの理解と要約・分析・回答、データ分析、コード作成など、幅広いタスクに活用できます。
特に、報告書の作成や膨大な資料の要約、顧客データや販売データなどの分析に活用したい場合におすすめの生成AIツールです。
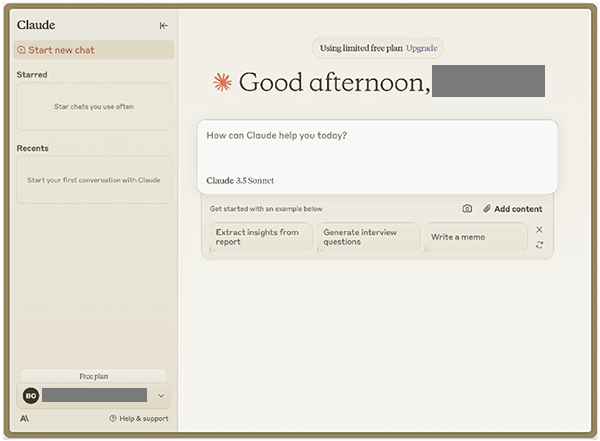
幅広いタスクに対応している生成AIツールですが、提案される回答や生成されるコンテンツが必ずしも完璧というわけではありません。
最後に、生成AIツールを活用するうえで注意すべきポイントやリスクについて解説します。
多くの生成AIツールでは、大量のデータから学習し、パターンを認識することで自動的に判断・予測・オリジナルのコンテンツを創出しています。また、継続的に新しいデータを学習することで、より賢く・多様なタスクに対応できるよう進化しています。
しかし、日々アップデートが行われている生成AIツールであっても、事実に基づかない情報や間違った情報を出力する「ハルシネーション」と呼ばれる現象を起こしたり、不適切な表現をしてしまう可能性があります。実際に、テキストフォームの画面内に「不適格な情報を表示することがあります」「間違いをする可能性があります」と言った注意書きが記載されている生成AIツールもあります。
また、多くのAIでは「temperature」と呼ばれるパラメータにより、出力結果に多様性・ランダム性をもたせる仕様になっているため、同じ指示を出しても出力結果が異なるなど、一貫性が欠如しています。
そのため、生成AIが回答した情報をそのまま鵜呑みにするのではなく、必ず目視による内容確認を行い、正しい情報であるか・適切な表現であるかを精査することが重要です。

① 著作権・商標権・肖像権を侵害するリスク
生成AIでは、インプットした大量の学習データをもとに、コンテンツを生成しているため、既存コンテンツと内容が似通う可能性があります。特に、Webサイトのテキストや小説、肖像、映像、音楽などが含まれている場合は、著作権・商標権・肖像権などを侵害する危険性があるため注意しましょう。
② 情報漏えいするリスク
生成AIが日々機械学習しているデータの中には、ユーザーがテキストフォームに入力した指示などの一連の会話が含まれており、第三者への出力に再利用される可能性があります。そのため、個人情報・顧客情報・自社の機密情報・製品開発といった、再利用されると情報漏えいになる・プライバシーの侵害につながる危険性が高い内容を入力しないよう注意しましょう。
③ プロンプトインジェクションによる攻撃へのリスク
プロンプトインジェクションとは、攻撃者が生成AIに対して誤作動を起こすような指示を送信することで、システムの設定や制約を回避し、開発者が出力を禁止している不正な情報を引き出したり攻撃者の意図する応答を生成させたりする攻撃のことです。
生成AIがプロンプトインジェクションの攻撃を受けることで、機密情報の漏えい・システムの不正操作・誤情報の拡散・サイバー攻撃の支援などに悪用されるリスクがあります。
使用している生成AIツールがサイバー攻撃を受けるリスクがあることを想定したうえで、情報漏えいにつながる情報は入力しない・出力された回答を鵜呑みにしないなど、注意する必要があります。

以上、生成AIツールの中でも多くのビジネスシーンで活用されている「ChatGPT」「Copilot」「Gemini」「Claude」それぞれの特徴や活用時の注意点について解説しました。
― 生成AIツールとは
― 生成AIツールの種類
― 生成AIツール「ChatGPT・Copilot・Gemini・Claude」の特徴
― 生成AIツールを活用するうえでの注意点・リスク
生成AIは、専門知識がなくてもクリエイティブなコンテンツを作成できたり既存業務の効率化に多く貢献するメリットの多いツールです。しかし、事実に基づかない情報を出力したり不適切な表現をしたりするなど、作成された内容が必ずしも完璧というわけではありません。また、情報漏えいや著作権の侵害といったリスクが伴っていることも忘れてはいけません。
生成AIツールを利用する際は、必ずテキストフォームに機密情報や個人情報といった情報漏えいにつながる内容を入力していないこと、生成された情報を鵜呑みにせず確認することが重要です。
また、従業員のセキュリティリテラシーを高め、適切・安全に生成AIツールを利用するために、自社のガイドラインを作成するなどのセキュリティ対策を講じることをおすすめします。